By�@���{�����@�i��A���̓��[�����z�[���y�[�W�̖����ɂ���A�h���X�܂ŁB�j
�E�F�u�y�[�W�f��: 2004�N�R��11���i�������M�\��j
�@�����قǂ̋��z�F�e�����ł����A�g���̑i�ׁh�Ƃ��Ă͖������Ȃ��Ǝv���܂��B�g���̎��āh�Ƃ��ẮA���Ȃ�̋��z���F�߂���ׂ������W�Ƃ͎v���܂����A����ł����z�����A�Ƃ͎v���܂����B�܂��A�����@35�����������Č_��̍S���͂��������߂�̂ɂ͔��ł��B����ɁA�č��̏Ƃ̔�r���A�]�肱��܂Ŏw�E����Ă��Ȃ��_�ɂ��Ď��݂܂����B
�i���̌�A���قł̘a�����c�₻�̌����ɂ��Ă����M���܂����B���łɐŋ��ɂ��Ă̌����������܂����A���Ȃ����������ǁB�j
�i2005�N6�����{���M: ��L�̐ŋ��̘b�A�{���ɉ����������悤�ŁA�C�����܂����B�j
�������̃R�s�[: 2003�N�X��19���n�ْ��Ԕ����@2004�N�P��30���n�ٔ���
�@�����Ɍ����āA�����܂ł̋��z���F�e�����Ƃ͎v���Ă��܂���ł����̂ŁA���������܂����B�ł��A��������ǂ�ŁA�܂�����Ă���Ƃ��납��������w�̋Ɛт��������āA�������x�܂Ŕ[�����܂����B�����قǂ̍D�ƐсB
�@2004�N�Q��14���i�y�j���j�̒����Ɍf�ڂ��ꂽ�Ƃ���ł́A�������w�̌o�험�v�i03�N12�����j�́A1000���~�̌����݁B���ꂪ�u�P�N�x�v�́u���v�z�v�Ȃ̂ł��B����ɔ�ׂĂ݂�A�����̌���604���~�Ȃ���200���~�Ƃ����̂��A�K�����������ɓ�����܂���B
�@�i�Ȃ��A���o�V���̋L������������ƁA�����̋Ɛтɂ��Ẵ��|�[�g���A�l���n���łɂ͕p�ɂɍڂ��Ă���̂��ڂɕt���܂��B�S���łɂ͂���قǂ͂Ȃ��̂ł��B�������w���A�l���̌o�ςɂ����đ傫�ȃv���[���X�������Ă��邱�Ƃ�\���Ă���悤�Ɏv���܂��B���v�z���A�l����No.�Q�Ȃ̂ł��ˁB���Ȃ݂ɂP�ʂ̓h�R���l���B�j
�@���̔����ɑ���ᔻ�I�Ȉӌ��Ƃ��āA�������̔��������ŗ��v���o��킯�ł͂Ȃ��A�]�X�Ƃ������̂�����܂��B���̒ʂ�ł��B�������w�̂��������N1000���~�I�[�_�[�̗��v�́A���̑啔�����F�k�d�c�ނɂ����̂Ƃ�����i����グ�̂W���A���v�̑唼���������ƕ��Ă��܂��j�A�����������v����悤�ɂȂ����̂́A�����Ē������̔����ɒ[��������܂��B�������A���̔��������ł��̗��v�ݏo���Ă���킯�ł͂Ȃ�����A�N1000���~�I�[�_�[��Ή��Ƃ���ׂ����̂ł͂Ȃ��B�c�c���������b�́A���ׂĂ����Ƃ��ł��B
�@�������A�����́A���z�Ƃ��ẮA���������c�_�ɂނ���]�������̂Ƃ������܂��i�����P���Ɍ����Ȃ��ʂ�����܂����A����͌�q�j�B���ӂ���ׂ��́A���������őS���łȂ��͂����Ƃ����̂́u�N1000���~�v�ɑ��Č����ׂ����Ƃ��낤�A�Ƃ������Ƃł��B����̔����̔F�e�z�͋��z�ł͂���܂����A���������ᔻ�̌����ʂ�A���̗��v�z�u�N1000���~�v�ɑ��ẮA�ق�̋͂��Ȋ����ɗ��܂�܂��B�g�[�^���ŋ͂��i�N1000���ɔ�ׂ�A�͂��j604���~�Ȃ���200���~��F�e�����ɉ߂��Ȃ����̂Ȃ̂ł��B
�@�������A�������g�̌���ė����Ƃ���ł��A93�N�̐F�k�d�c�J���́u���E���������v���ƂȂ̂ł����i�u1993�N�ɐ��E�����������FLED�̔��\�B�v�ƁA���N�i�r�̓������w�̃y�[�W�ɏo�Ă��܂��A���͂����փ����N���܂����j�A���݂̍D�Ɛт���������������Ƃ������̂ł���͔̂ے肷�ׂ�������܂���B���������Ӗ��ł́A���z�̕�V���s�v�c�ł͂Ȃ��͂��ł��B
�@�܂��A����������Ƃ̗��v�̌����Ƃ����_���猾���āA����قǂ̋��z�������Ή��Ƃ��ĔF�߂��邱�Ƃ́A�ő��ɂ��邱�ƂƂ͎v���Ȃ��A����A���ɂ�����Ƒz�����o���܂���B��Ƒ�����̃R�����g�Ƃ��āA���z���F�߂����ł͊�ƌo�c�Ƃ��č���A�Ƃ�������|�̂��̂����������܂������A�I�O��Ȕᔻ�ł��B����قǂɔ����Ŗׂ��Ă����Ƃ́A���{�ɑ��ɖw�ǖ����ł�����i��O�̓p�`�X���Ƃ�����? �j�B�܂��A����قǂɖׂ����Ă��邩�炱���̋��z�ł�����A�����Ȃ����Ƃ̐S�z�͕s�v�ł��B���ہA�������w�̎x���\�͂͂܂��������Ȃ��͂��ł��B�N�Ԕ���グ1800���~�ɑ��Ă͌��\�����������܂����A���͌o�험�v1000���~�i�I�j�Ȃ̂ł�����B
�@����ł��A�����܂ŋ��z�Ȃ̂͋����ł͂���A���ɂT����F�߂��̂́A�u���̎��āv�ɂ��Ă��^��ł͂���܂��B�������A�u���̑i�ׁv�Ƃ��Ă͂�����ɋ^��ł͂���܂���B�����̎咣�ɖ�肪����Ǝv������ł��B
�@�����Ƃ����������̂́A�������}�C�i�X�P�T���~�Ƃ̎咣�ł��B�������w�̒�o�����A�V���{�č��@�l�̊Ӓ菑�i���P�P�V�j�ł��i���ꎩ�̂͏o�Ă��Ȃ��̂�(�����㗝�l�̏��i�搶�̎������̃y�[�W�ɂ́A���鎞���܂ł͏؋��Ȃǂ��f�ڂ���Ă���̂ł����A����͌�������Ȃ�)�A�����ǂ�ł͂��Ȃ��̂ł����j�B
�@�����牽�ł��A�������̕]���Ƀ}�C�i�X�Ƃ����̂͂Ȃ��ł��傤�B�����̎��т̗��v�z����J���o��������ƃ}�C�i�X���Ƃ����v�Z�̂悤�ł����A�������A���ꂪ���̔����̉��l�i�Ή��j�Ƃ����̂͂��������ł��B���Ƃ��J���Ƃ��Ėׂ���Ȃ������Ƃ����v�Z�ɂȂ낤�Ƃ��A����ł��������̂̉��l�̓}�C�i�X�ɂ͂Ȃ�܂���B�܂��������ł́A�T�����Ă���J���o��͈̔͂ɂ��^�₪����Ǝw�E����Ă��܂��B�V���{�č��@�l�́A�肻�ȋ�s�̊č��̍ۂɂ��A�J�艄�אŋ����Y�̊W�Œ����č��@�l�ƑΗ������o�܂����Ă��܂����B�{���Ƃ͊W�Ȃ��Ƃ͎v���܂����A�˗��҂̌������Ƃ��߂��̂悤���Ƃ̈�ۂ�ۂ߂܂���B
�@�������w�̕��ł́A�����Ƒ��ɂ��F�X�Ȏ咣�͂��Ă���悤�ł͂���܂����A�������A���̂悤�ȃ_���Ȏ咣�Ɠ����ɂ����̂ł́A�����͂��������ł��傤�B���������咣�헪�́A����ł͂Ȃ������悤�Ɏv���܂��B����̑��̎咣�̐����������p���Ĕے肵�Ă��܂����ʂɂȂ������̂��Ǝ��ɂ͑z������܂��B
�@�����̎咣���w���A�Ƃ����̂́A���܂��ł����낢�댾���Ă���Ƃ���ł��B�o�T�����炩�łȂ��ł����A�ǂ����̌f���̔�������̈��p�ŁA���̂悤�Ɍ����Ă��܂��B�Ȍ��ɖ{����˂��Ă���Ǝv���܂�:
�@�u���v-15���v�u�S�R�g���˂������v�u����͓Ǝ����@�v�u���ꂪ�ǂ�ȕ��@���͂����Ȃ��v�@�@�Ƃ��������̃~���N��DQN�ŗ��h���܂ŏ���Đ����ɂȂ��Ă��܂����Ƃ�����Ղ̔����B
�@�܂��A����������ɂȂ��Ĕ��������̂ł����A�c���ې��́u�C���^�[�l�b�g�œǂ݉���!�v��2004�N3��11���t���̃y�[�W�ɁA���x�ȏ�Ɠ��l�́A�����̎咣���������āA�ٔ����ɂ͑��ɑI�������Ȃ������A�Ƃ����������悭��������Ă��܂��B�����Ƃ����Ǝv���܂��B
�@�ڂ����͌�Ɍ������܂����A���̔����́A���z�I�ɂ͒Ⴍ����悤�ɓw�͂��Ă���Ƃ��猩����ʂ�����܂��B604���~�Ȃ���200���~�Ƃ������z��F�肵�����̂ł͂���܂����A���̔F��v���Z�X�ł́A�ɗ͋��z��}���悤�Ƃ��Ă���悤�Ɍ�����̂ł��B�u���ߔ��㍂�v���v�Z���Ȃ�����A���ǂ́A�������g�̗��v���Ȃǂ�F�肷��ɂ͎������s�����Ƃ��āA���ЂɗL�����������ꍇ��z�肵�A���̑Δ��㍂�ł̃��C�����e�B�����Q���Ƃ��āA���̌��_�Ƃ���1200���~�]���F�肵�Ă��܂��B���̔����Ƃ���604���~�������Ή��A�Ƃ̔F��ł��B�u�Q���v�́A��ʓI�ɂ͍��������ł����A�����̌o�c���тɔ�ׂ�ƒႢ�ł��B���㍂�ɂ��Ă��A2003�N12�����̎��тƔ�ׂāA���ɍT���ڂ����邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă��܂��B
�@�������w�́A���݂͂��̔��������{���Ă��Ȃ��Ƃ����咣�����Ă��܂��B�����ł͂��̎咣�͈�R����Ă��܂��Ă��܂��B���̕ӂ�̋c�_�́A�ǂ����������w�̕��ɂ́A�Z�p�I�͈͂̑������Ɍ��������悤�Ɋ����܂��B����A�i��搶�i�������w�̑㗝�l�j�͏d�X�����m�̂͂��ł�����A�܂����������咣�����݂��Ƃ������ƂȂ̂ł��傤�i���Ɏ��̎����F������������A�̘b�ł����j�B
�@�����̕s���{�̎咣�́A�{�������ɋ�̓I�ɊJ������Ă�����@�Ƃ͈Ⴄ�A�Ƃ�����|�̂悤�Ɏv���܂��i�������̒��ł͎��̒ʂ�: �u�퍐�̎咣����Ƃ���́C�v����ɁC�m�E�n�E�ɌW�镔���̍\�����t������Ă��邩��C�퍐�����@�́C�{�����������Ƃ͋Z�p�v�z���قɂ���S���ʌ̔����ł���Ƃ������Ƃɐs������̂ł���v�j�B���������̕��@�ɂ��Ă��A�{�������̕��@�����ɂ��ĉ��ǂ������̂ł���̂͊m���Ȃ悤�ł��B����Łu�����������ǔ����v�Ƃ���܂����B�c�[�t���[�i�����K�X�ɉ����āA�s�����K�X�̃t���[���g�������ŁA��҂őO�҂���ɉ����t����Ƃ������́j�ł���ɂ͈Ⴂ�Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B���̔�������{�I�Ȃ��̂ŁA�������L���Z�p�I�͈͂ł����Đ������Ă���ꍇ�ɂ́A���̖����ɂ����čl�����Ă��Ȃ��悤�ȕ��@�ł����Ă��A���̎��{�ł���ɂ͈Ⴂ�Ȃ��킯�ł�����A�����Ȃ�͓̂��R�ł��B
�@���̉��ǂɐi����������Ȃ�A������ɓ������������邱�Ƃ�����܂��B���������ꍇ�ł��A���̊�{�����̋Z�p�I�͈͂ɑ�������̂ł���Ȃ�A���̎��{�̂��߂ɂ͊�{�����̕��̃��C�Z���X���K�v�ɂȂ�܂��i���ǔ����̕��̃��C�Z���X���K�v�Ȃ̂͂������ł��j�B���������W���u���p�����v�Ƃ����܂��B
�@��s�Z�p�̏�����������ꍇ�ɂ́A��{�����̓����́A�͂��ȗv�������ŋK�肳�����̂ɂȂ蓾�܂��B���̏ꍇ�ɂ́A�L�ĂȎ��{�ԗl���Z�p�I�͈͂ɑ�������̂ƂȂ�܂��B�v�V�I�Ȕ����̉��l�́A���̌��ʁA�ƂĂ��傫�����̂ƂȂ�̂ł��B
�@����̔����ł́A����404�����̏d�v����S�ʓI�ɔF�߂܂����B����ɂ́A�����̋^�����������̂ł͂���܂��B����Ȍ�̑����̔�����m�E�n�E�J���������Ď��{����Ă���Z�p�ł��邩��ł��B�������A������404�����̋Z�p�I�͈͓��̂��̂Ƃ����͖̂ܘ_���蓾��b�ŁA�܂��A������ЂƂ̊W��404�����������d�v�Ƃ����̂��\���ɍl������Ƃ���ł��B���ɁA�ߎ��͓������w�͋�����ЂƂ̓����i�ׂŕ��������Ă��܂������i404�����͑i�ׂɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��j�A404�����������d�v�Ƃ����b�ɂ��Ȃ�̂ł��傤�B
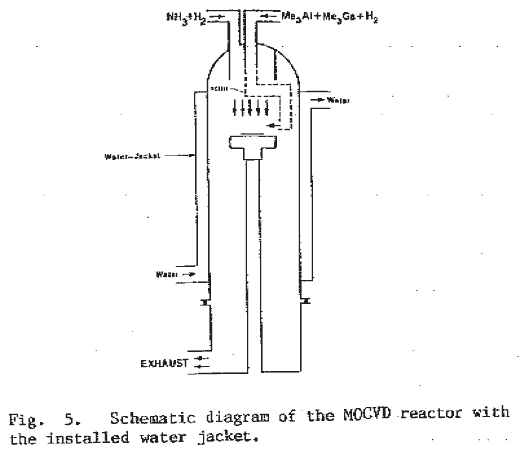
�@�c�_�Ƃ��ẮA�{�������͗]���{�I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��A�����̎��{�̗L���f����ɓ������Ă��A�]�蒊�ۓI�ɋ��ʐ����l����ׂ��ł͂Ȃ��A�Ƃ����咣�����蓾�܂��B���̎|�̃��[���Ղ��A��s�Z�p�����̃t�@�N�X�����������܂����B
�@����́A�{�������̒��ł����̂悤�Ɍ��y����Ă��镶���ł��B���̊̐S�̐}�T�����Ɍf�ڂ��Ă����܂��B
�@12�@���◝�R�ʒm�ƕ
�@�@�@�����C�����o�蒆�ł������{�����������ɑ��C�����W�N�W���Q�Q���t���ŋ��◝�R�ʒm���i���P�O�S�j��������ꂽ�B���̋��◝�R�ʒm�́C���m�����ł���uJournal of Electronic Materials,14�k5�l�i1985�j�v�i���P�O�R�j�����p������C�������̑�T�}�iFig.5.�j�ɂ́C���������̓��������͈̔͂ɋL�ڂ��ꂽ�����Ɠ���̔����̌������̐������@���L�ڂ���Ă���|���w�E������̂ł������B
�@�@�@�퍐��Ђ́C��L���◝�R�ʒm���āC���N�P�P���P�U���t���ňӌ����i���P�O�T�j���o���C��L�����̑�T�}�ɋL�ڂ��ꂽ�����̌������̐������@�́C��Ɍ������ĕ��s�ȕ����y�ѐ����ȕ����̗������甽���K�X�˂��C�����̌������𐬒���������̂ł���̂ɑ��C�o��ɌW�锭���́C��ɐ����ȕ����ɔ����K�X���܂܂Ȃ��s�����K�X�������K�X�Ƃ��ċ������鑊��_������|�̈ӌ����q�ׂ��B�܂��C�퍐��Ђ́C�����t���Ŏ葱����i���P�O�U�j���o���C�����ɂ�������������͈̔͂̋L�ڂ��C���L�̂Ƃ������邱�ƂȂǂ���e�Ƃ������s�����B
�@�@�@�u���M���ꂽ��̕\�ʂɁC��ɑ��ĕ��s�Ȃ����X��������ƁC��ɑ��Ď����I�ɐ����ȕ�������K�X���������āC���M���ꂽ��̕\�ʂɔ����̌������𐬒���������@�ɂ����āC��̕\�ʂɕ��s�Ȃ����X��������ɂ͔����K�X���������C��̕\�ʂɑ��Ď����I�ɐ����ȕ����ɂ́C�����K�X���܂܂Ȃ��s�����K�X�̉����K�X���������C�s�����K�X�ł��鉟���K�X���C��̕\�ʂɕ��s�Ȃ����X��������ɋ�������锽���K�X����\�ʂɐ����t��������ɕ�����ύX�����āC�����̌������𐬒������邱�Ƃ�����Ƃ��锼���̌������̐������@�B�v
�@���̐}�͊m���ɁA���悤�ɂ���Ă͂��Ȃ�߂��ł��B�}�̏�[�̍����痈��K�X�͍L�����ŏo��̂ɑ��āA�E����̃K�X�͓_���ŋL���ꂽ�p�C�v��ʂ��Ċ�Ղ̏�ɉE�����痬����܂��B���悤�ɂ��܂����A�_���p�C�v����̃K�X�́A�L���̕�����̃K�X�Ŋ�Ղɉ�����������i�D�ɂȂ肻���ł��B
�@���������m�ɈႤ�̂́A���̍L���̕��̃K�X�̓A�����j�A�K�X���܂�ł���̂ɑ��āi��������NH3�Ə����Ă���j�A�{�������́u�s�����K�X�v���g���Ƃ��Ă���_�ł��B��L�̔������p�����Ő�����Ă���R���o�߂ł��A���̓_���咣����Ă����킯�ł��B�܂��A��s��ɂ́A���������\��������|�Ƃ������A�𗧂ĕ��ɂ��Ă̊J�����\���ɂ���킯�ł͂Ȃ��A����������s�Ⴊ�����Ă��{����������������͓̂��R�Ƃ͎v���܂��B
�@�������A�����͂����Ă��A�K�X�̃t���[���Q����ɂ͈Ⴂ���Ȃ��A�߂��Ƃ����߂��B������A����ƈႤ�Ƃ̎咣�̌��ʂƂ��Đ��������{�������́A������ɂ͍L�ĂȌ�����F�߂���ׂ����̂ł͂Ȃ��A�Ƃ͌��������ł��B���Ƃ��A�t���[���Q�����Ă��A���̎g����������Ă��āu�s�����K�X�v�łȂ��Ȃ�A���{�i�ł͂Ȃ��Ƃ̋c�_���傢�ɉ\�Ǝv���܂��i�f��ł���悤�Șb�ł͂���܂��j�B
�@����������Ɠ����̌����@�͖{���͂����Ȃ̂����m��܂��A���������Ȃ��Ƃ��A�{�������̂܂Ƃߕ����炷��ƁA�����ł͂���܂���B�܂��A�����͂��������咣�����Ă����킯�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B�����ł́A�u�퍐�����@�v�̕��ł��u�m�E�n�E�ɌW�镔���̍\�����t������Ă���v�����A�Ƃ���Ă���̂ł��B
�@���ǁA�{�������́A�t���[���H�v����Ƃ������Ǝ��̂œƑn�I�A�Ƃ������ɓƑn�I�ł͂Ȃ��ɂ��Ă��A���̓����͂�͂�\���ɈӋ`������̂ŁA�傫�ȉ��l��F�߂���A�Ƃ������Ƃ̂悤�Ɏv���܂��B
�i�ȏ�A�⑫�j
�@���̂悤�ɓ����̎咣�ɂ͎����ȂƂ��낪����Ǝv���̂ł����A�ł���͂�A���̔����ɂ��^��ȂƂ��낪����܂��B���_�́A�����́A���݂��猩�Ă̔����̉��l����ɂ��āA���̂T����Ή��Ƃ��ĔF�߂Ă��邱�Ƃł��B
�@��L�̂悤�ȗ��p�����̐����Ȃǂ��l���Ă������邱�Ƃł����A�������Ƃ����̂́A����I�ɋZ�p�J�����i�ނ��Ƃɂ���ĉ��l�����߂邱�Ƃ�����܂��B���Ƃ��A�����ɂ͎��ƂƂ��Ďg���悤���Ȃ��Z�p�ł��i�������L���Ȓ��x�ɂ͎��{�\�ł��A�������ۂ̎��ƂƂ��Ă͖����A�Ƃ����Z�p�͂��蓾�܂��j�A���p�Z�p�����܂��Ă����ƁA�g�����ʂ������Ă����Ēl�ł����o�Ă���A�Ƃ������Ƃł��ˁB
�@���̈�̓T�^�Ƃ��āu���p�����v�̏ꍇ���l���邱�Ƃ��o����킯�ł��B���̔����ōl�����Ă����܂��J������Ă������{�ԗl�Ƃ͈���Ă��āA�����ɐi������������̂ɂ́A���̔����̋Z�p�I�͈͓��̂��̂ł����Ă��A���p�����Ƃ��ĕʂɓ������F�߂���邱�Ƃ�����܂��B���p�����ɓ��������������ꍇ�ł��A��������{����ɂ́A���̕��̊�{�����̋������K�v�ł��B�܂��A��{�����̌����҂��A���̗��p�����̌`�Ԃł̎��{�̂��߂ɂ́A���p�����̕��̓����̋������K�v�ł��B
�@�����������p�����ɍ������p��������ꍇ�ɂ́A����ɂ���āA��{�������̂̉��l�����܂�܂��B���p�����̎��{�ɂ́A��{�����̋������K�v������ł��B
�@�t�ɁA�Z�p�I�͈͂ɑ����Ȃ�����Z�p���J�������ƁA�����̉��l�͏������Ȃ�܂��B����Z�p�̌������������̂��ƁA�܂������l�ł��������Ȃ��Ă��܂����Ƃ����蓾�܂��B
�@���������ꍇ�ł��A���������͕̂ς���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃɂ��蒅�ڂ���ƁA���l���ς���Ă���A�Ƃ��������̎d��������̂͏o���Ȃ��Ȃ�܂��B�{�������́A�����Ȃ��Ă���悤�Ɍ����܂��B�������A���ۂ𗦒��Ɍ���Ȃ�A�l�ł����ω����Ă���Ƃ������Ƃ��Ǝv���̂ł��B
�@�������̒l�ł��́A�O���I�ȗv���ɂ���ĕϓ�����A�Ƃ������Ƃł��B
�@���āA�����@35���ɂ��A�]�ƈ������҂Ɏx������ׂ��́u�����̑Ή��v�ł���A������g�p�҂́u���v�̊z�v��u�v���������x�v���l�����Č��߂�ƂȂ��Ă��܂��B���߂Ĉ��p���Ă����܂�:
3 �]�Ǝғ��́A�_��A�Ζ��K�����̑��̒�ɂ��A�E�������ɂ��Ďg�p�ғ��ɓ������錠���Ⴕ���͓����������p�����A���͎g�p�ғ��̂��ߐ�p���{����ݒ肵���Ƃ��́A�����̑Ή��̎x�����錠����L����B
4 �O���̑Ή��̊z�́A���̔����ɂ��g�p�ғ�����ׂ����v�̊z�y�т��̔����������ɂ��Ďg�p�ғ����v���������x���l�����Ē�߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@����̔����łǂ����^��Ȃ̂́A�g�p�҂̊l���������v�̊z�ɁA�����ґ��̎�蕪���|�������̂����̂܂ܑΉ��̋��z�Ƃ��Ă��܂��Ă���悤�Ɍ�����_�ł��B���ɁA�{���͂��Ȃ���قȌo�܂Ŕ������Ȃ���Ă��āA��Ђ͗]�苦�͓I�ł͂Ȃ������̂ł����i���w��u�w���̓_�ł͂���Ȃ�̍v�������Ă���Ǝv���̂ł����A���ǂ̂Ƃ����Ђ̖��߂Ō������Ă����킯�ł͂Ȃ��_���ǂ����Ă����ڂ���Ă��܂��܂��j�B����ŁA�������̂ɂ��ẮA��Ђ̍v���͂������������A�Ƃ����b�ɂȂ�A�����͂����1200���~�̔����i��Ђ̍v���������Ƃ��Ă̎c�锼���j�̐�����������ƔF�肵�Ă���킯�ł��B
�@����������́A35���̋K�肵�Ă���Ƃ���Ɩ{���͈Ⴄ�悤�Ɏv���܂��B�������̂̐����ւ̍v������������Ƃ����Ȃ��Ă��܂��܂����A����͈Ⴄ�̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃł��B35���̋��߂Ă���̂́A��{�I�ɂ́u�����̑Ή��v�̎x���ł��i�R���j�B�����āA���̋��z���g�p�҂́u���v�̊z�v��g�p�ғ����u�v���������x�v���l���ɓ���Č��߂�A�ƌ����Ă�����̂ł��i�S���j�B�����A�u���v�̊z�v�̂����g�p�ґ��̍v�������������̂̑S�����҂Ɏx�����A�Ƃ������Ƃɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��Ǝv���̂ł��i���̎�|�́A���ɋg�c�a�F�u�E�������Ɓw�����̑Ή��x�Ɋւ�����v�m�a�k779���S�ł��A�u���ߘ_�Ƃ��ẮA�B�ɂ��ẮA�@�O���l���́A�u�g�p�ғ�����ׂ����v�̊z�v�Ɓu�g�p�ғ����v���������x���l�����āv��߂邱�Ƃ�v�����Ă��邪�A����ȊO�̗v�f�̍l�����ւ��Ă���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA��l�̗]�n�����낤�B�v�Ǝw�E���Ă���j�B�S���ł������Ă��闘�v�z����юg�p�҂̍v���ȊO�̃t�@�N�^�[���l�����āu�����̑Ή��v�������邱�Ƃ́A�@�ɔ����Ă��Ȃ�����łȂ��A�R���̋K�肩�猾���Ė@35��S�̂ɂނ��뉈�������̂��Ǝv���܂��B
�@���������ϓ_����́A�܂��́A���̂悤�Ȏ�����l���ɓ���邱�ƂɂȂ�܂��B1200���~�Ȃǂ̉��l�̂́A��Ђ����̔��������Ɖ����A���ꂪ���܂����������Ƃ̌��ʂł��B���̉ߒ��ł́A���̔����𗘗p���鑼�̓������������Ă��܂����A�܂����ۂ̎��Ƃ��s���ɍۂ��Ă͑����ɑ����̃m�E�n�E�J�����K�v�ł��邱�Ƃ́A����̔��������F�߂Ă��܂��B���������w�͂������ď��߂āA�傫�Ȏ��ƂƂȂ�傫�ȗ��v�A�����������ł͂���̂ł��B��������������l���ɓ����ׂ��ŁA50����������Ȃ��A�Ƃ����͕̂s�K�̂悤�Ɏv���Ă��܂��B
�@�����A����ɍl����ƁA�ʂ̕����̘b���o�Ă��܂��B�����������Ɖ��ɂ������Ђ̍v���͊m���ɂ������Ƃ͎v���܂����A���́A�x�X�g�������킯�ł͂Ȃ��悤�ɂ��v���܂��B���̓_���l����ƁA�����̋��z�����ނ��낳��ɑ��₷�ׂ��Ƃ̘b�ɂȂ��Ă��܂��ʂ�����܂��B�Ƃ����̂́A�������w�͍ŋ߂܂Ń��C�Z���X���܂��������Ȃ��ŗ��܂����B���ꂪ�A�{�������̐��������p�̎d�����������ǂ����ɂ��ẮA���Ȃ�^�₪����܂��B
�@����ł�����Ȃ�̎��ƋK�͂ɂȂ��Ă��Ă͂��܂����A���������ɁA�{�������𑁊��Ƀ��C�Z���X���Ă���A�����e�Ђɂ���čX�Ȃ���NJJ�����Ȃ���A��{�����Ƃ��Ă̖{�������̉��l�͂�荂�܂����\��������Ǝv���̂ł��B�ꕔ�Ŏw�E����Ă���Ƃ���ɂ��A�����������C�Z���X���Ȃ���Ă���A�����Ƒ����Ɍu�������쒀����悤�ȏƖ��p�����_�C�I�[�h�����p�����ꂽ�̂ł͂Ȃ����A�����u�����Ȃ�ĂȂ��Ȃ��Ă̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����b���炠��܂��B
�@�����������C�Z���X����肭����Ă���A���ƋK�͂��������X�ɑ傫���킯�ł�����A�{�������̒l�ł��͂����Ƒ傫���Ȃ��Ă��������m��܂����i�������A���̂悤�Ƀ��C�Z���X���Ȃ�����A����Ȃ�̃��C�����e�B�����ێ�����ȂǁA�F�X�O������͕K�v�ł͂���܂����j�B���ɂ����Ȃ�ƁA���������̎�蕪�́A50�p�[�Z���g���͔䗦�ł͒Ⴍ�Ȃ��Ă��A1200���~�Ƃ��ꂽ���̋��z�������Ƒ傫���Ȃ��Ă����A�Ƃ����\��������܂��B
�@��������������ɊS���ƁA����ɁA�{���̔����������������̎��_�ɂ�����A�������̂��̎��̂̉��l�Ƃ��ẮA�ǂꂾ���̂��̂������̂��A�Ƃ����ƁA����͌��݂Ƃ͈Ⴄ�̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���Ă��܂��B����ł��������x�ɍ������������m��܂���ǁA����{���̏ꍇ�͂��Ȃ�͍����������̂Ƃ͎v���܂����A����قNj��z�Ƃ͌�����Ȃ������̂ł͂Ȃ��ł��傤��?
�@�܂�A���E���������Ƃ͌����Ă��{���ɂ��̂����ő傫�Ȏ��Ƃ��������邩�ǂ����͒肩�łȂ������Ǝv���̂ł��B���ۂɗǂ����i���o���邩�ǂ����́A�����s���������͂��ł����A�ʂ̋����Z�p�i��������ǂ����́j���������邩�ǂ�����������Ȃ��킯�ł��B�������A�Z�p�I�͈͂���O���ʂ̂����ŁA�����Ɨǂ����̂��o�ꂵ����A�����̉��l�͖����Ȃ��Ă��܂��܂��B�����������̂��o���邩�ǂ����Ƃ����̂́A�ȒP�ɂ͕�����Ȃ��ł��傤�B�������Ă݂�ƁA���̊J���̎��_�Ŗ{�������̉��l��]��傫���ƌ�����͖̂����A�Ƃ������ƂɂȂ�悤�Ɏv���܂��B
�@����̔������́A�{�������̓o�^������Ƃ���ƌ����Ȃ�����A����14�N�܂ł̎��т���э���̐R���̒��ŏo���ꂽ���̎��_�ł̕���15�N�x�ȍ~�̗\���Ɋ�Â��ĉ��l��F�肵�Ă��܂��B�o�^����Ƃ����̂́A���ԗ������T������Ƃ������z���������̎��Ȃ̂ł��ˁB�������A���͒��ԗ����ł͂Ȃ��Ǝv���̂ł��B���ɂȂ�̂́A��L�̂悤�ȁA���ʂ��̕s�m�����A���ƂƂ��Ă̐����̌��ʂ��̓���A�������l������ł̂܂��ɂ��̎��_�ł̔����̉��l��F�肷��ׂ��ł͂Ȃ��̂��A�Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B
�@�����Ƃ��A���̓_�ɂ��Ă��A���������������Ƃ������́A�����҂̎咣�������������̂ł����Ȃ������A�Ƃ������Ƃ̂悤�ɂ͎v���܂��B
�@�ꉞ�͈ȏ�̂悤�Ɏv���̂ł����A���̕�����]��ɓO�ꂷ��ƁA�p���Ċ�Ȃ��ƂɂȂ�\��������Ƃ͎v���܂��B���Ɖ��ɓ�����������ł̎��v�́A�������̂̉��l�Ƃ͕ʂł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃ�˂��l�߂Ă����ƁA���ׂĂ̎��Ǝ��v��ʈ����ɍl���邱�Ƃɂ��Ȃ肩�˂܂���B����Ȃ��Ƃ�����ƁA�����̔����̒l�ł��Ƃ����̂��l�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂����m��܂���B���X�����̒l�ł��́A���炩�̌`�Ŏ��Ƃ��Ƃ��Ȃ��Ă����̂��̂ł͂���̂ŁA�����˂��l�߂�A�Ƃ����̂͂��������b���Ƃ͎v���܂��B���R�̎��Ɖ��ɂ���ē����闘�v�́A�ނ���A�����̕��ɒl�ł��������Ă̎��v�ł���ƌ������ŁA���̕ӂ�������I�ɍl����K�v������Ǝv����킯�ł��B
�@����̔����́A���̎��_�i����14�N���т܂ŏo�Ă��鎞�_�j�ł̔����̉��l��F�肵�Ă���50���𑊓��̑Ή��Ƃ��Ă��܂��Ă��܂��B������������F��̂��߂Ɏg�����Ƃ��������Ƃ͎v���̂ł����A���v�̎��т����̂܂܌��ɂ��đ����Ή����v�Z����̂́A�������Ă��Ȃ��A�Ƃ����̂����̍l���ł��B
�@���������_�ŁA�{��������604���~�Ȃ���200���~�͍��z������\��������܂����A����������ł��A�����ȍ��z���F�肳���ׂ����̂��Ƃ͎v���܂��B�{���̔����̏ꍇ�ɂ́A�����̓����������I�ȋƐт��Ƃ͂����Ă������̂ł��̂ŁA���Ȃ�̑Ή��͔F�߂���Ƃ͎v���A�Ƃ������Ƃł��B
�@�{�������̓����́A���z�̐�Ίz�����邱�ƂȂ���A�����ҁi���������j�̍v����50�p�[�Z���g��������Ȃ��Ƃ̔F��ɂ���܂��B����50�p�[�Z���g�̓_�́A�����̓����ɂ����ĉ�Ђ����͓I�łȂ������i�������Ďז����Ă��j�Ƃ������Ƃ����ɑ傫�ȃt�@�N�^�[�ƂȂ��Ă��܂��B����͎����̂悤�ł����A����������Ђ̌����Ƃ��Ďn�܂������Ƃʼn�Ђ̋����g���Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��A�܂��A���̌�̎��Ɖ��ɂ����ĉ�Ђ̖������Ȃ��킯�ł͂Ȃ��A�ނ���A��Ђ��ϋɓI�ȓ��������Ď��Ɖ��������炱���A�����̉��l�����̂悤�ɍ��܂����A����́A�F��Ȃ����؋��Ƃ��Ă̖�肾���ł͂Ȃ��āA���ۂɔ����̒l�ł����̂��̂����Ɖ���ʂ��č��܂����̂��ƌ���ׂ��Ȃ̂��낤�Ǝv���̂ł��B
�@�܂��A���̂悤�ȔF������邱�Ƃɂ���āA���̒��ł̔ᔻ�Ɉ�����x�����邱�Ƃ��o�������ł��B�ᔻ�Ƃ��āA���Ƃ��A���̂悤�Ȃ��Ƃ������Ă��܂�:
�u�@�F�k�d�c�ł͐ԍ�E����勳�����͂��߂Ƃ�����s�����̍v�������邵�A�f�q���珤�i�ւ̍H�Ɖ��A�̔��w�͂Ȃǂɑ����̐l�Ԃ��֗^���A�H�v��n�����������ɈႢ�Ȃ��B���Ƃ��Z�p�J�������������i���o���Ă��K���������i�ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂��r�W�l�X���B�l�A���m�A�J�l�̌o�c�����𓊓�������Ƃ͕s�m���Ȍo�c���X�N�ƕ������킹�ɂȂ��Ă���A����ɑ����V�͏������Ȃ��͓̂��R���B�v
�i�����K��u�F�k�d�c�����͏�O��t�@�E���\�\�u�E�������v�������ċc�_���i�j�S�j�v2004/02/16,���{�o�ϐV���@����,5�y�[�W����j
�@���������펯�ɂ͂����Ƃ��ȓ_������܂����A���s��35���́A������\���Ɏ�荞�ނ��Ƃ̏o����K�肾�Ǝv���܂��B�u�����̑Ή��v�̎x�������߂Ă���̂ł���A���̎Z��ɂ͎w�E����Ă���悤�Ȏ��������ׂ����Ǝv���邩��ł��B
�@����������ɂ��Ă��A�������̉��l��傫�Ȃ��̂ƌ���_�ɂ��ẮA�{�������ɂ܂������^���ł��B�������w�̋Ɛт�����Ɣ[���������܂����A�L�͂ȓ������������Ă��Ă������v���オ��̂ł��ˁB�����łȂ���A������Ƃ������ɎQ�����Ă��āA�������v�����ێ�����邱�Ƃ͂��蓾�܂���B���������Ӗ��ŁA���������������v�̌���ł���A�ׂ���Z�p�Ȃ̂ł���A���̌o�ϓI���l�͋ɂ߂đ傫���̂ł��B�����A���������ꍇ�ł����Ă��A���̔����҂ɂ��ׂĂ��A������킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�u�����̑Ή��v�́i�����ɓ������Ẳ�Ђ̍v�����������j�S���ƂȂ�킯�ł͂Ȃ��A�Ƃ����̂����̎w�E�ł��B
�@���āA���̔����̑O����A�����@35���̉������c�_����Ă���A������ɂ͒�o�����ƕ���Ă��܂��B���̉����Ă����\�����Ȃ��̂ŁA���O�̌_��Ɍ��͂�^���悤�Ƃ�����̂ł͂���̂ł����A���ꂪ�����Đ�ΓI�ł͂Ȃ��̂ŁA����Ƃǂꂾ���Ⴄ���ƂɂȂ�̂�����b�ɂȂ��Ă��܂��B�܂�́A����ł��u�����̑Ή��v�Ƃ����Ă邾���ŁA����͖��炩�ɑ傫�ȕ��̂�����̂ł�����A����Ȃ�̋��z����Б����x�����Ă���ꍇ�ɂ́A�ٔ����͂���𑊓��̑Ή��͈͓̔����Ƃ���\�����傢�ɂ���Ǝv���܂��B���������̂�⋭��������̉����ł͂���܂����A�������A�����I�łȂ��Ƃ��Ĕے肷��]�n���c���Ă���킯�ł��B
�@���������A�����Ă̌��E���w�E����_�l�������A���o�V���Ɍf�ڂ���Ă��܂����A�ʈ�搶�̘_���ł��i2004/02/03�̓��o�����E�o�ϋ����j�B�u�����@�́w�����̑Ή��x�K������S�P�p����K�v������B�v�u���������������o�������Ă�������Ăł͕s�\���v�ŁA�u���O�_���S�ʓI�ɑ��d����č��^�V�X�e���v������A�Ƃ̂��咣�ł��B����ɂ���ď��߂Ď��O�\�����m���ɂȂ�Ƃ̂���|�͋ɂ߂Ę_���I�ł��B
�@���������͔��ł��B
�@��ɂ������Ă�������ẮA���O�_�u�����I�v�Ȃ炻��ɏ]���A�u�����I�v�łȂ��ꍇ�͍ٔ������u�����̑Ή��v��F�肷��A�Ƃ����d�g�݂ł��B����ł͕s�\���Ƃ����̂��ʈ���ł����A�ł͋ʈ���ɏ]�����ꍇ�ɉ�������Ă��邩�ƌ����A�u�����I�v�łȂ��Ă��S���͂��F�߂����悤�ɂ���A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�������A�����I�łȂ��Ă��`�A�Ƃ����̂ł́A����͂��܂荇���I�Ȑ��x�ł͂Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
�@����Ɍ����A���s�@�ł��u�����v�̑Ή��ƋK�肵�Ă�����̂ł���A���ꎩ�̂͂����s���ł͂Ȃ��͂��ł��B�����ς���K�v������Ƃ̋c�_�́A�u�����v�łȂ��ėǂ��A�ƌ����Ă��邱�ƂɂȂ�킯�ł���A�^��ł��B���������Ӗ��ŁA�������̖@�Ă͌��s�@���ƃh���X�e�B�b�N�ȈႢ���������̂Ƃ̗������o���܂����i������ʈ�搶�ɔᔻ������ł����j�A��������R�ł��B�u�s�����v�ɂ���@�ĂƂ����͖̂���������܂�����B
�@����ł��A���̖@�����́A���O�_���d����������ւ́A��̂��������ƂȂ�\���͂���܂��B�����A�������F�e����Ă��錻�݂܂ł̗L�����Ăł́A���ɕ����Ă�����z�������~�ȂǁA����u�����v�ƌ����Ȃ����̂��ڗ����Ă���킯�ł��ˁB�����������Ăɂ��ẮA�@�������Ă�����ς�u�����I�v�łȂ��Ƃ��āu�����v�z���F�肳��邱�ƂɂȂ肻���ł��B������ʈ�搶�͔ᔻ����킯�ł����A���͂���͈Ⴄ�Ǝv���܂��B�ނ���A�����̊e��Ђ̐E���������x��������x�́u�����I�v�Ȃ��̂ɉ��߂��Ȃ�����A���d�����킯���Ȃ��A�Ƃ������Ƃ̂悤�Ɏv���܂��B
�@����̔����ł́A200���~���F�e����܂������A����́A�\���I�����̂��̂Q�ɂ����̂ł��B���������͎�ʓI�ɂ́A�{���������̈ꕔ�i���L�����j�̈ړ]�o�^�����߂Ă���A�܂��\���I�����̂��̂P�ł��A�Ή��Ƃ��ē��l�ɋ��L�����̈ړ]�o�^�����߂Ă��܂��i�Ή��Ƃ��Ď��������߂Ă�����́j�B�{�������ɕč��łȂ�ǂ��Ȃ������Ƃ����ƁA�Ή������̌����݂͔����ł����A��ʓI�����̕��Ɉ�����x�̉\�����������A��������ɂ��ꂪ�F�߂�ꂽ�ꍇ�ɂ͑傢�ɈӋ`������A�Ƃ����w�E���o���܂��B�����W�ɂ������Ă��܂�����n�b�L�����܂��A���Ȃ��Ƃ��A���{�ł̂悤�ɍŏ����疳���Ƃ����̂Ƃ͈Ⴂ�܂��B
�@�{���̎�ʐ����́A�������錠�������n���Ă��Ȃ�����A�������������҂ɂȂ�ׂ����A�Ƃ��������ł��B����������́A���{�̌��s�̖@���x�ł͓���F�߂��܂���B����͓�̕������炻���ł��B��ɂ́A35���ɂ�葊���̑Ή��̐������o����̂�����_��ɏ��n���ӂ�F��ł���Ƃ������Ƃ�����A������́A���ɏ��n���Ȃ��Ƃ�����A�����������ɂȂ邾���ŁA�ړ]�o�^�����Ƃ��������͂�����Ɩ������A�Ƃ������Ƃł��B
�@���ɓ������錠�������n���Ă��Ȃ��Ƃ��Ă��A�����������g�͓������o������Ă��Ȃ��킯�ł��ˁB�{�������͂����܂ł���Ђ��o�肵�Đ����������̂ł��B���ɁA�������錠���̏��n���Ȃ������Ƃ���ƁA���̉�Ђ̓����͖����ƂȂ�܂��B�ł��ꂾ���ł��B�����ƂȂ邱�Ƃ͂����Ă��A���������Ɉړ]����Ƃ��������́A�ǂ�������o�Ă��܂���B���������������������o�肵�Ă��āA���ꂪ�s���Ɉړ]�o�^�܂��͖��`�ύX���ꂽ�ꍇ�ɂ��Ă͓������̓o�^��Ԋ҂�����]�n������̂ł����i���ɂ����������������܂��j�A�{���ł́A�ŏ�����o�肵�Ă���͉̂�Ђ̕��ł�����A�����������������铹�͂�����ƍl�����Ȃ��킯�ł��B
�@���ɏo������Ă���͓̂������w�ł�����A���Ђ��������錠��������Ă��Ȃ��Ƃ�����A���̏o��Ɋ�Â��Ă̓����͖����ɂȂ�܂��B�������A������Ƃ����āA���������̕��͏o�肵�Ă��Ȃ��̂ł�����A���������闝�R�͖����ƌ������Ƃł��B
�@���������킯�ŁA��ʓI�����́A�����������ꐬ�藧�������ɂȂ��b�ł��B
�@����ɁA���{�̏ꍇ�A���L���������Ƃ��Ă��A���������̂悤�Ȍl�ɂƂ��ẮA�܂������o�ϓI�Ӗ�������܂���B
�@��ʐ�������ї\���I�����̂��̂P�ł́A�������e�Ƃ��ẮA���L�����̈ړ]�o�^�����߂Ă���A���������ꂪ�F�߂�ꂽ�ꍇ�ɂ́A���L�̏�ԂɂȂ�킯�ł����A�������A�l����ЂƓ����������L���Ă����ʂ̓����b�g�͂܂���������܂���B�Ƃ����̂́A�������̋��L�̏ꍇ�A�e���L�҂͎��玩�R�Ɏ��{���邱�Ƃ��o���܂����A���C�Z���X�����邱�Ƃ́A����ɂ͏o���Ȃ��̂ł��B�����̋��L�҂̓��ӂ��K�v�ƂȂ�܂��B
�@�l�Ƃ��ẮA������{���邱�Ƃ͏o�����i���Ǝ����������ł�����j�A���Ƃ����đ��҂Ƀ��C�Z���X���邽�߂ɂ́A�����̋��L�҂̓��ӂ��K�v�ƂȂ��Ă��܂��̂��i�����@73���R���u�����������L�ɌW��Ƃ��́A�e���L�҂́A���̋��L�҂̓��ӂȂ���A���̓������ɂ��Đ�p���{����ݒ肵�A���͑��l�ɒʏ���{�����������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�v�j�A�ǂ��ɂ��Ȃ�Ȃ��̂ł��B
�@���̈���ŁA�������w�̕��͎�����{���邽�߂ɂ͉��̎x��ɂ��Ȃ�Ȃ��i�����@73���Q���u�����������L�ɌW��Ƃ��́A�e���L�҂́A�_��ŕʒi�̒�������ꍇ�������A���̋��L�҂̓��ӂȂ��ł��̓��������̎��{�����邱�Ƃ��ł���B�v�j�A�Ƃ����ł�����A���L������^���Ă��܂��l�����Ă��܂������Ӗ��������̂ł��ˁB
�@�ȏ�̓�_�ɂ��āA�č����Ƃǂ�����b���܂���������Ă���̂ł��ˁB�܂��A�č��̎d�g�݂��ƁA�ړ]�o�^�����̕������_�I�ɉ\��������܂��B�����҂��o��l�ƂȂ��Ă��Ȃ������i�s���ɃI�~�b�g����Ă����j�Ƃ����ꍇ�ɂ��āA������C������Ƃ����\�����A�����@�̏�ł����L����Ă��܂��iSec. 256. - Correction of named inventor�A���̓R�[�l���փ����N�A���̃R�s�[�j�B�������錠�����A���{�������͂Ȃ�ł��ˁB�����҂̈ꕔ������n���Ă��Ȃ��`�ł̏o�肪�Ȃ��ꂽ�ꍇ�ɁA���n���Ă��Ȃ������Ҏ��炪�������҂ɂȂ蓾�܂��B
�@����͎��̑z���ł����A�������������{�ł͖����ƍl�����Ă��鐿������ʓI�����Ƃ����̂́A��ɂ́A�\���I�����̂��߂̍��̂悤�Ȃ��̂�����̂ł��傤����ǁi���̗L�����͋^��ł����j�A������ɂ́A���ݕč��ɋ��邽�߂ɂ�����̕�����̉��炩�̃A�h�o�C�X�������߂ɁA���������v�������悤�ƍl����Ɏ������̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����̂��z������܂��B
�@�܂��A�{���̒��Ԕ����ł́A�������錠���̈ړ]��F�߂�ɂ��āA�u�����̑Ή��v�𐿋��ł��邱�Ƃ���̍m��I�v�f�Ƃ��Ă���悤�ɗ�������܂��B���Ȃ킿: �u���������āC�����@�R�T������́w�_��C�Ζ��K�����̑��̒�x�ɊY������_�ɑ����Ή��Ɋւ���������u����Ă���C���Y�����̓��e�������R���C�S���̎�|�ɔ�������̂ł������Ƃ��Ă��C�]�Ǝғ��́C�Ή��̕s���z�𐿋����邱�Ƃ��ł���ɂƂǂ܂�C�����̕s�����𗝗R�Ƃ��āC���Y�_�ɂ��������錠�����̎g�p�ғ��ւ̏��p�̌��ʂ𑈂����Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ƃ����Ă��܂��B���̔����́A�������������g�s��������S���̂ɂ��Ď����̑��ւ̓����̕Ԋ҂�F�߂�h�Ǝ咣����̂ɑ��Ẳ����ł���A�����Ή����F�߂���̂�����ړ]�͗e�Ղɍm�肳���A�Ƃ�����|�Ɨ����ł��܂��B
�@����ɕč��̏ꍇ�ɂ́A���L�҂ɂȂ��������ŁA���̋��L�҂���̓��ӂ�K�v�Ƃ����ɑ��҂Ƀ��C�Z���X�����邱�Ƃ��o���܂��iSec. 262. - Joint owners�A���̃R�s�[�A�ł́A���̎|�̖��L�͂Ȃ��̂ł����A���̗l�ɉ�����Ă��܂��j�B����͌o�ϓI�ɋɂ߂ĕs�����Ȑ��x���ƌ����Ă���A�܂����ۂ����Ȃ�ł����A�Ƃɂ������{�̏ꍇ�Ƒ傫������Ă��܂��B�ł�����A�č��̎d�g�݂Ȃ�A�������������L��������A����Ɋ�Â��ĖL�c�ʏ���N���[�ȂǂɃ��C�Z���X���邱�Ƃ��o���Ă��܂��킯�ł��B
�@�č��ł́A���s�@��������@35���R���͂Ȃ��̂ŁA�w�ǐ��_��ɂ���Ĕ����̋A����Ή��̎���͌��܂邱�ƂɂȂ�A�{���̂悤�ȑΉ������͐��藧�������ɂ���܂���B��L�̂悤�ɋʈ䋳���Ȃǂ͂�����x��������̂ŁA���̘_�|�ɂ�������x�����Ƃ��ȂƂ��낪����̂͊m���ł��B�������A��L�̒ʂ莄�͔��ł����A����ɁA�����ŋL�����悤�ɁA�č����͉�Б��ɗL���Ƃ͌���܂���B�Ȃ��Ȃ������[���Ƃ��낾�Ǝv���܂��B
�@�����搶�́A���@�ł́u�⏞�v�ƈ���āA���s�̏��a34�N�@�ɂ����Ắu�Ή��v�Ƃ��ꂽ���Ƃ������Ƃ��āA���n�̎��̉��l�ɂ��ׂ����Ǝ咣���܂��B���̌��_�ɂ͎����^���ł��A���������̌��t�̈Ⴂ�������ɂȂ�悤�ȋC�͂��܂���B�⏞�Ƃ����ꍇ�ł��A�������ړ]����邱�Ƃ̏����Ƃ��ẮA�㕨�Ƃ��Ă̎x���`�����K�肵�Ă����̂ł���A������̎��Ƃ̐��ʂ��^���Ȃ�������Ȃ��Ƃ����b�ɂȂ�킯�ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�ނ���t�ɁA�Ή��Ƃ������t�ɂ��Ď��́A���̉��l�̑S�����ׂ��A�����Ă��̂��߂ɕ]��������ɂ́A��̐��ʂ����邵���Ȃ��A���ۂ̎��Ƃ��痣��Ē��ۓI�ɉ��l�����߂�͖̂������A�Ƃ����c�_�ɂȂ�����̂������܂��B
�@�{�����ǂ��Ȃ̂��Ƃ����̂́A�c�_�̗]�n����������肾�Ǝv���܂����A���̕ӂ肪�m���ɖ��̂���Ƃ��낾�Ǝv���܂��B����������ɂ��Ă��A������������N�������ҁi��Б��j����\���ɂȂ��ꂽ�킯�ł͂Ȃ��悤�Ɍ����܂��B���ɁA���ɖׂ����Ă���͎̂����ł���Ƃ���ɁA�ł͂ǂ����Ėׂ����Ă���̂��ɂ��č����I�Ȑ������Ȃ���Ă��Ȃ��B����ŁA�d�v�Ȕ������������Ƃ͂܂��ԈႢ�Ȃ��Ɨ�������邩��i�����������̔������킴�킴�I��Œ�N���Ă����Ƃ�����������Ă��܂��j�A��Ђ̕��ŁA���v�̌����̓����ł͂Ȃ����Ƃ�������Ȃ��ƁA�ނ��낻�̓����ɑ傫�Ȓl�ł����{���I�ɑ��݂������̂悤�Ɍ����Ă��܂��A�����F�肳��Ă��܂��A�Ƃ����̂��d�����Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
�@������A���̎����̂��̍ٔ��ɂ��ẮA�����������������蓾��Ƃ����̂����̗����ł��B�������Ȃ���A��̎��Ƃ̗��v���A���R�Ɋ�b�Ƃ��ĎZ�肷��̂��ǂ��Ǝv���킯�ł͂���܂���B����́A�{�e�̏�̕��œ������猾���Ă��邱�Ƃł��B���Ƃɂ����Ėׂ���Ɏ������A���̔����ȊO�̂��̂̊�^�Ƃ������̂��v�Z�ɓ���邱�Ƃ�������đR��ׂ��ł���A���������Ӗ��ł́A���̑i�ׂł͓����҂������Ƃ�����咣���Ă��Ȃ������悤�Ɍ����邩�画�������r�Ƃ͎v��Ȃ����A�����������Ƃ͉��߂čl����ׂ����Ƃ͎v���̂ł���A�����搶�̂��w�E�i���_�����j�ɂ͎����܂������^���ł��B
�@���R����Ɛ��{����̌����u�E�������i�ׂɂ�����\���I�Ȗ��i�P�j �\ �u�F�����_�C�I�[�h�i�ׁv���Ƃ��ĈˑR��肪�����E�������i�א��x�v��ǂ݂܂����B�L�����ɋ^�₪����A��������Ɖ��l����������̂͑Ó��łȂ��A�Ƃ����̂͂����Ƃ��ȓ_�̂���w�E�ł��B�ł��A�č��̘b�����̂܂ܓT���̂悤�ɂ���̂́A���Ȃ�s�v�c�ł��B�L�����ɂ��ẮA���x�I�ɂ����l�Ƃ͌����Ȃ����B
�@�c�c���e�I�ȃR�����g����ʼn��M���܂��B
�@�l���V���̂����ɁA�P���W���t���ŁA�������قł̘a�����c�ɂ��ĕ��Ă��܂��B���Q�V���i���}�́j�ł��A���|�̋L����ǂ݂܂����B�S�����ɂ͖����悤�ł�����A�l���ł̒��ړx�̍������f���܂��B
�@���z�́A�u�T���\�P�T���v�Ƃ̂��ƂŁA�����ƕ��̂���b�ł��B�ʂ����Ă���Řa�����c�͐i�ނ̂��낤���B�܂��A���̋��z�ɂ��ẮA�u���z�̎x�������������w�̌o�c�ɗ^����e���Ȃǂւ̔z������A�a�����z�͈�R�����n�ق��x�����𖽂����Q�O�O���~��啝�ɉ����z�ŋ��c�v�Ƃ���Ă��܂����A����ᕥ���Έ��̉e��������ɈႢ�͂���܂��A��������������������Ƃ��������A�|�Y�����˂Ȃ��悤�ȃC���p�N�g�̂悤�ɋ����܂��B�������A���v�̔N�z���牭�~�I�[�_�[�Ȃ̂ł�����A���̐S�z�͖����͂��ŁA�]�萳�����Ȃ������̂悤�Ɏv���܂��B
�@�����̗��v�z���l����ƁA���́u�T���\�P�T���v�Ƃ̋��z�͕K�������\���ł͂Ȃ��悤�ɂ��v���܂��B�������A���Ɖ��ɂ���ĒB���������݂̓������̉��l�́A���������̉��l�Ƃ͕ʁA�Ƃ̏�L�̍l���i�������j���炷��ƁA���Ȃ�Ⴍ�Ȃ��Ă����������Ȃ��킯�ł��B����ł������̗��v�����z�Ȃ̂ŁA���̋��z�ł͍���Ƃ��v���̂ł����A����ɗL�����ɋ^�₪�����ł͂Ȃ��Ȃǂ̗v�f����������ƁA���ǂ͂��̂��炢���Ó��Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤���B
�@�i1��10�����M: �����̓��o�V���ɂ́A�P�ʂɁA���̘a�����̘b�����Ă��܂����B���Ȃ��l�b�g�ł������ɂ���܂��B��L�̎l���V�����Ƒ�̓����悤�ȓ��e�ł����A���z�͂U���~�Ƃ���Ă��܂��B�n�ق̔F����z��100����1�ł��B�j
�@�i2��27�����M: ���ق̘a���������A�����̃y�[�W�Ɍf�ڂ���Ă����̂Ń����N���Ă����܂��B����ł��B���L���b�V���B�@4��4���lj��A���ق̃y�[�W�ɂ��o�Ă܂��ˁB���̃L���b�V���B�j
�@�ĊO���������? �A�a�������������̂ł��ˁB�܂��́A�����������ʂ����t�������炱���A�������ĐV���L�����o���Ƃ������ƂȂ̂����m��܂���B
�@���������́A���ς�炸�������R�����g�����Ă���悤�ł����A���̋��z�́A�܂��A�펯�I�ł͂���̂ł��傤�B�T���Ƃ����̂́A���X�N���Ƃ��Ă��Ȃ��]�ƈ������҂Ƃ��ẮA�����Ƃ��Ȍv�Z�ł��B��L�̂悤�ɁA�傫�ȉ��l�ݏo�����Ƃ��Ă��A����͂��̌�̎��Ɖ��ɂ�镔�����傫���̂ł���A�]�ƈ������҂���̈ړ]���_�ł̑Ή��Ƃ��ẮA���̒��x�ɂȂ�̂͏\���ɍ����I�ł��B�C���������������10���Ɣ�ׂĂ��܂����i���L���b�V���j�A���\�ǂ��w�E���Ǝv���܂��B�u��ǂތ���A�T���͏��Ȃ�����̂��Ƃ��v����v�Ƃ����A�u���z�̕�V�����߂�Ȃ�A�Ζ����i������A�N�Ƃ��ă��X�N�����ׂ����v�Ƃ̈ӌ��Ɏ^�����Ă��܂��i�ł��l�d���ĂƂ���������ǁj�B
�@����ł��A�������w�̌���̗��v�͔N�z���牭�~�I�[�_�[�Ɨ]��ɋ��z�Ȃ̂ŁA����ɔ�ׂ�Ƃ�����Ə��Ȃ��悤�ȋC�����܂��B�ǂ��܂ł����������̍v�����琶�܂�Ă���̂�����ł����A�Ƃɂ����A�����̂P�N�Ԃ����̗��v�̂T�����v�Z���������ł��A50���~�ɂȂ��Ă��܂��̂ł�����B
�@�{���̌o�߂Ɋւ��ẮA�c���ې������������Ă���悤�ɁA�n�قł̉�Б��̎咣���܂��������̂��낤�Ǝv���̂ł��i���L���b�V���j�B
�@�i2��27�����M: �ٌ�c�̌����Ƀ����N���Ă����܂��B���L���b�V���B�j
�@���̘a���Ŗʔ����̂́A�x�����Q�������Ă��邱�Ƃł��B��ʓI�Șa�����ł́A�x�����Q���͂܂����܂���ˁB�퍐���ɑ��āA�����Ȃ炻����t�����ǁA�a���ɉ�������̕��͈����Ȃ�A�Ƃ��������̘a���̃C���Z���e�B�u�Ɏg�����Ƃ������Ǝv���܂��B
�@�{���̌��o�܂̏ڍׂ͕�����܂��A���Ă���Ƃ��납�炷��Ƃǂ����A�x�����Q���������̕�����ςݏグ�������݂����ł��ˁB�퍐�̉�Ђ̕��ł��A���ڂƂ��đ�R�����̂���������Ƃ����l�����������悤�ŁA�x�����Q���Ƃ��ĕ��������ނ���e��₷���������悤�Ɍ����܂��i�Ƃɂ����A�������͕̂s���R�Ȃ������Ђł�����j�B�����O��Ƃ��āA���̕��������㗝�l�̐搶�̕�V�ɍs���낤�A�Ȃ�Ęb�����邱�Ƃ�����܂��A���̐Ȃł̘b��Ƃ��āB�z���g���ǂ����͒m��܂���B
�@���ǂ͍��v���z������ɂ͈Ⴂ�Ȃ��ł�����A�����������ڂ�����̂́A�Ŗ���̈������l���Ă̂��ƂȂ̂��Ȃ��A�Ƃ����̂����͍ŏ��v���܂����B�����v�����̂́A�{�������͌��݂͔Z�҂Ȃ̂ŁA����Ȗ�肪���邩��Ȃ��A�Ƃ����̂��A���g��c�������ɑz����������ł�����܂��B�ł��A�ȉ��ɋL���悤�ɁA���������Ӗ��ł̎��v�͋^��Ɏv���܂��B
�@�܂��A�[�Ŏ҂ɗL���ȉ\�����l����ƁA�u���Q���v�Ƃ������Ƃ���A�x�����Q�����͏����ɂȂ�Ȃ��Ė��ŁA�Ƃ����̂��ł��L���ł��ˁB���Ƃ��Ό�ʎ��̂̐l�g���Q�̔����͔�ېłł����i���Ƃ����^�b�N�X�A���T�[�̂����ɐ���������܂��A���L���b�V���j�A����́A���������̂̑�����Ƃ��������A�Ƃ�������������A�ېŏ����ɂȂ�Ȃ��Ƃ������ƂƎv���܂��B����ɑ��Ēx�����Q���͎����͗��q���Ǝv���܂��B���łƂ����͖̂����ŁA���Z�҂Ȃ�G�����Ƃ����i �����Ŗ@23���̗��q�����̒�`����͊O��܂��j�A�Z�҂Ȃ��L��161��6���̏����Ƃ��āA�ېł����悤�Ɏv���܂��B
�@�������A��ʓI�ɑ��Q�����̏ꍇ�A�x�����Q���������ېłƂ��Ă���킯�ł͂Ȃ��āA�S����ېł̈����̂悤�ɂ��v���܂��i�悭�m��Ȃ��̂ł����B�l���Ă݂�ƁA���ɂȂ�قǂ̒x�����Q���������̂͒������Ƃ������Ƃ����邠��Ǝv���܂��j�B��������ƁA35��Ή��̒x�����Q���������ł��悢�̂����m��܂���B���������A���łƏo����\�����l���āA�x�����Q���Ƃ������̂ł��傤��? �ł���͂�����͗��q���Ǝv���܂����A�����O��Ƃ���ƁA��q�̂悤�ɁA���Ȃ��Ƃ����{�ł̌����ɂ��ẮA���s���đd�ŏ��͋t�ɕs���Șb�ɂȂ�悤�ł��B����Șb�����m��܂���B
�@����őd�ŏ��̘b�ł����A���傤�Ǎ�N�A���đd�ŏ��������āA�ȑO��茹�������肳���悤�ɂȂ�܂����B�V��ƁA�Z�҂Ȃ�A�x�����Q���ȊO�́u�Ή��v�ɂ��ẮA���������\���͂Ȃ����̂ƌ����܂��B�����ɐV���̉���A�����R�s�[�B�g�p���ɂ��Ă��A�]�O�͌y���ŗ�10���������̂������Ȃ������A�K�肪����ȊO�͍����o�d�A������������ېł��Ȃ��Ɩ��L����܂����B�ȑO���Ƌc�_�̗]�n���������Ǝv���̂ł����B
�@�i���{�̏����Ŗ@��́A�����̔Z�҂ɑ��ẮA�����Ŗ@161��7���C�́u�� �@�����ɂ����ċƖ����s���҂���鎟�Ɍf����g�p�����͑Ή��œ��Y�Ɩ��ɌW����́@�C�@�H�Ə��L�����̑��̋Z�p�Ɋւ��錠���A���ʂ̋Z�p�ɂ�鐶�Y�����Ⴕ���͂����ɏ�������̂̎g�p�����͂��̏��n�ɂ��Ή��v�Ƃ��āA�g�p���ƑΉ��͂ǂ���������̑ΏۂƂȂ�܂��B����Ɋւ��ẮA�����ŏ����ʼnېł���������d�g�݂ɂȂ��Ă��܂��A169�������170���ȂǂŁB�����Ŗ@�̌������Ɛŗ��Q�O���ł����A�d�ŏ��Œጸ���ꂽ��[���ɂȂ����肵�܂��B�j�B
�@�Ƃ��낪�A�ł��B�V���ł��A���q����10���̌���������̂ł��ˁB�x�����Q���́A���̈Ӗ��ł͗��q�̈�킾�Ǝv���̂ł����A�ǂ��Ȃ̂ł��傤? �����Ŗ@23���́u���q�����v�̒�`�ɂ͊Y�����Ȃ��ł����i�G�����ɂȂ�͂��j�A���e�I�ɗ��q�ɂ͈Ⴂ�Ȃ��ł�����A�d�ŏ��̗��q�ɂ͂�����Ǝv���܂��B�Z�҂ւ̎x���ɂ��ẮA�����Ŗ@161��6���́u�Z �@�����ɂ����ċƖ����s���҂ɑ���ݕt���i����ɏ�������̂��܂ށB�j�œ��Y�Ɩ��ɌW����̗̂��q�i���߂Œ�߂闘�q�������B�j �v�ɂ����肻���Ɍ����܂��B�{���̌����͑ݕt���ł͂Ȃ��ł����A��������̂ɂ͂Ȃ�̂ł͂Ȃ��ł��傤��? ����Ƃ��A�x�����Q���͌����͂���Ȃ��̂��Ȃ��A���Ƃ��G�����ɂȂ�ɂ��Ă�����͂���Ȃ��Ƃ��������A����������͗ǂ��ł��ˁB
�@���Ɍ�������Ă��A������̕��́A�č��ł̐\���ɂ����ĊO���Ŋz�T���ł���͂��Ȃ̂ŁA���ǂ͖{�l�ɂƂ��Ă͕ς��Ȃ��̂������ł��B�ł����A���Ƃ��R�X�g����R���������ꍇ�Ȃǂɂ��i���ہA�ٌ�m��V���������ł����j�A�O���Ŋz�T���Ŏg����Ȃ��\�����[���ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�����łȂ��Ă��A�킴�킴���q�ɂ���̂́A���{�̐ŋ��̊W�ł͏��Ȃ��Ƃ��L���Ȃ킯�ł͂���܂���B�܂��A�{���͘a�������Ƃ͂����A���������ҊԂł́A�葱���ɂ��ċ��͂������Ȃ������肵�Ă�������Ȃ��Ƃ����蓾�܂��B���ہA���̌��Ō�������ƁA���ɂ�������O�ɑz�肵�Ă��Ȃ������̂ł���A���ꎩ�̂������ɂȂ肻���Ȍ����ȏł���ˁB
�@�č��̕��ł́A���Z�҂ł���ȏ�̓��[���h���C�h�C���J���ɉېł����킯�ŁA���Ȃ킿�A�ǂ��������ېłŏ����łƂ��Ă����邾���Ŗ��ڂ͖��W���낤�Ǝv���̂ł����A����������ƁA�č��ł̉ېł̍ۂɂ́A���q�̕����L���ɂȂ�d�g�݂�����̂����m��܂���B�ǂ��Ȃ낤? �܂��A���ʂȐ��x�͂Ȃ��Ă��A���Q�����Ƃ��Ĕ�ېł̉\�����l���Ă���̂����m��܂���A��L�̂Ƃ���B
�@���ɖ�肩���m��Ȃ��Ǝv���̂́A�����̊W�ł��B�����͍��͔Z�҂ł����A���̔����������Ƃ��⌠���̏��n���������Ƃ��́A���Z�҂������킯�ł��B���܂��܉������������Ēx�ꂽ�����i����A�{���͂��̑i�ׂ��n�܂����Ƃ��ɂ͊��ɔZ�҂ł�����A���̌������̓w���Ƃ����w���ł����j�A�ƍl����ƁA���{�ʼnېłł��Ȃ��̂͂��������i���q�ɂ��Ă̌������������ېłł��Ȃ��͕̂s���j�A�Ƃ����̂���̌��������m��܂���B����ȏ�ɂǂ��������������蓾��̂��͎��ɂ͕�����܂��B
�@����Ɍ����A���̏���i�����ɂ��Ă̋c�_�̏�Łj���^�������ƐŖ����ǂ��咣����ƁA�������ł����i����A�s�搶�����w�E�ɂȂ����Ƃ��ɂ͂܂����Ǝv���܂������A��q�̂悤�ɃX�g�b�N�I�v�V�����̘b�Ɣ�ׂ�ƒP�Ȃ��k�ł͂Ȃ������j�B�t�Ɉꎞ�����ɂȂ�\��������Ǝv���̂ł����B�ꎞ�������Ɓi�����̏��n�����Ɠ������j�Ŋz�v�Z�������ɂȂ�̂ŁA�����ԏ��Ȃ��Ȃ�܂��ˁB��̃X�g�b�N�I�v�V�����̃P�[�X�ŁA���ǂ͍ō��قŋ��^�����ɂȂ��Ă��܂������Ƃ��炷����i�٘_�����ł̔����\��Ȃ̂ł����Ȃ錩�ʂ��ƕ��Ă��܂��j�A�{���ł����^�����ɂȂ�\���̓[���ł͂Ȃ�? �i�����Ɩ��W�Ȃ̂Ŗ��ӔC�Ȃ��Ƃ������Ă��鎄�B�j�@���������̏ꍇ�ł��A�č��̕��ł��ق��Ă���Ƃ͎v�����i�����̖��Ƃ��Č����_�̏����ƍl����̂́A����͂���ŏ펯�I�ł�����j�A��������ېł̃��X�N�������Ă��܂������m��܂���B�������K�v�Ƃ������ƂɂȂ�܂��ˁB
�@��������̉ېŊW�́A�����̏ꍇ�ł��悭������Ȃ����Ƃ����X����̂ł����A���̃P�[�X�͊O���ւ̈ڏZ�܂ł�����ނ̂ŏ�����A���̏�킴�킴�x�����Q���Ɩ������Ď����肷����̂�����A���ɂ��낢��ȉ\��������܂��B���ꂩ��܂��i�ׂɂȂ����肵�āB
�@�i05�N6�����ɉ��M: �x�����Q����ʌv��ɂ�����|�Ƃ��āA�{���̑Ή������^�����Ƃ���Ă��܂��ƁA�o��v�オ�o���Ȃ��̂ŁA���̍ň��̏ꍇ�̑Ώ��A�Ƃ����̂�����̂����m��܂���B�����Ƃ��A���̏ꍇ�ɂ́A�ٌ�m��p�̂����̂ǂꂾ�����A�x�����Q���̌o��ɏo����̂��A�Ƃ������蓖�Ă̖�肪���������ł��B�j
�@�ŋ��̘b���A����������ƌ������Ă݂܂��B�{���ł͍��͔Z�҂ɂȂ��Ă��܂����A������������͗�O�I�ł��̂ŁA���ʂ̍��������̏ꍇ���l���܂��B����͖{���Ƃ͈ꉞ�͈Ⴂ�܂����A��L�̂悤�Ɏ����̖��̑������ɂ���Ă͊W���邩���m��܂���B
�@�����Ŗ@33���i���@�߃f�[�^�V�X�e���̕����猩�Ă��������B�����Ŗ@�͂����j�́A�u���n�����Ƃ́A���Y�̏��n�i�������͍\�z���̏��L��ړI�Ƃ���n�㌠���͒��،��̐ݒ肻�̑��_��ɂ�葼�l�ɓy�n���Ԏg�p������s�ׂŐ��߂Œ�߂���̂��܂ށB�ȉ����̏��ɂ����ē����B�j�ɂ�鏊���������B�v�Ƃ��Ă��܂��B35��Ή��́u�������錠���v���̑Ή��ł���A���������������u���Y�v�ł����āA���́u���n�v�u�ɂ�鏊���v���A�Ƃ����̂͗������ʂ��Ă���悤�ɂ��v���܂��B ��������ƁA�Ŋz�̌v�Z�ɍۂ��ẮA�u���������z���瓖�Y�����̊���ƂȂ����Y�̎擾��y�т��̎��Y�̏��n�ɗv������p�̊z�̍��v�z���T���v���ď����z���v�Z���i33��3���j�A���̏�ŁA�ېŕW���̌v�Z�̍ۂɂ͂T�N�ȏ�ۗL�̒������n�i���������ߎw��̏ꍇ�������j�Ȃ�ېŕW�������z�ɂȂ�܂��i22���j�B
�@����ŁA�������ǂ����A���Ȃ킿�u���̎��Y�̎擾�̓��Ȍ�ܔN�ȓ��v���ǂ������A�ǂ̂悤�ɍl����̂������ɂȂ�̂��Ǝv�����̂ł����A�Ƃ��낪�A���̒�`�ɂ́u�i���߂Œ�߂���̂������B�j �v�Ƃ̊��ʏ������t���Ă��āA35��Ή��ɂ����Ă͂܂肻���Ȃ��̐��߂����݂���̂ł��ˁA���́B�����Ŗ@�{�s��82�����u�i�Z�����n�����͈̔́j �攪�\��� �@�@��O�\�O���O����ꍆ �i�Z�����n�����j�ɋK�肷�鐭�߂Œ�߂鏊���́A���Ȃ̌����̐��ʂł���������A���p�V�Č����̑��̍H�Ə��L���A���Ȃ̈琬�̐��ʂł���琬�Ҍ��A���Ȃ̒���ɌW�钘�쌠�y�ю��Ȃ̒T�z�ɂ�蔭�������z���ɌW��̌@���̏��n�ɂ�鏊���Ƃ���B�v�Ƃ��Ă��āA�����̑��݊W�́A���������������Ȃǂ��������A�Ƃ����b�Ȃ̂ł��ˁA�ǂ����B����ł����͓̕��ɂȂ�A���z�Ōv�Z�����A�Ƃ������Ƃ̂悤�ł��B�i6��24���ɏC���A����ȊO�ɂ�����Ȃ�ɏC���j
�@�ǂ����A���̎{�s��82���́A���o���̕t�������炢���ƁA�����ɏ����Ă�����̂��Z���ɂȂ��Ă��܂��悤�Ɍ�����̂ł����i���̌�����Ƃ��ẮA����œ����͓ǂ݊ԈႢ�܂����j�A���Œ��̃z�[���y�[�W�u���Œ��̂s�`�w�A���T�[�v| http://www.taxanswer.nta.go.jp/3152.htm�@No.3152�@���n�����̌v�Z�̂�����(�����ې�)�A���L���b�V���A������ƁA���Ȃ̌����̐��ʂł���������Ȃǂ������Ƃ��Čv�Z����Ă��܂��B
�@���ǁA���̎{�s�߂̋K��ɂ��A�u�擾�̓��v�����l����܂ł��Ȃ��A�������n���͂Ȃ�Ȃ��Y�������i6��24���ɏC���j�̂ł��ˁB�Ȃ��A�u�������錠���v�͈Ⴄ�A�Ƃ����̂��`���_���Ƃ��Ă͂��肩���m��܂��B
�@���_�Ƃ��ẮA��L�̐��߂̗p�ӂ����Ă��A���n�����i�����j�Ƃ���ׂ����̂ƍl�����Ă���悤�ŁA�m���ɂ��ꂪ�����������ǂ������ł��B���ꂾ�ƁA�擾����p���T�����āA50���~�i�ȓ��j�̓��ʍT�������āA����̓̈���ېŕW���Ƃ��ĐŊz�v�Z�����邱�ƂɂȂ�܂��B�Ȃ��A���n�����ɂ��ẮA��ʓI�ɂ͑d�œ��ʑ[�u�@�ɂ����Ⴊ���낢�날�����i�����A���ꂪ��ʓI�j�A�����Ŗ@�ɂ�镔�������Ȃ��قǂł����A35��Ή��ɂ��Ă͑[�u�@�͓��Ă͂܂���̂͂Ȃ��Ǝv���̂ł����A�悭������܂���B
�@�i�ȏ�A6��24���Ɍ��_���܂������C�����܂����BS���烁�[���ł��w�E�����������A�{�s�߂̋K��̎�|�ɗ������Ă����炵�����Ƃ��������߂ł��BS����A���w�E���ǂ������肪�Ƃ��������܂��B�Ȃ��A�r����́A������F���Ƃ����ł��J�݂Ȃ����Ă����łł��B�j
�@�i6��24�����M: �������n�ƂȂ�炵�����Ƃ���A���̍��̈Ӗ��͖w�ǂȂ��Ȃ��Ă��܂����A����ł��A�������ł͂Ȃ��Ƃ��ď��n�����łȂ��Ƃ����\�������邩��A�܂������̃[���ł͂Ȃ��Ƃ��v���̂ŁA�c���Ă����܂��B�j
�@����ł��A�u���Y�̏��n�v�ł͂Ȃ����낤�Ƃ����������A��ɔے肳�����̂ł��Ȃ��ł��傤�B��L���߂��A35��Ή���{�|�Ƃ���킯�ł͂Ȃ��āA�l���Ƃł̌����ɂ�锭������ȑΏۂƑz������܂��B���ɏ��n�����łȂ��Ƃ���ƁA�ꎞ�����ƂȂ�\�����o�Ă��܂��B���ꂾ�ƁA�ېŕW���������ɂȂ�̂ŗL���ł��i22���j�B�ꎞ�����̒�`�́A�u��O�\�l�� �@�ꎞ�����Ƃ́A���q�����A�z�������A�s���Y�����A���Ə����A���^�����A�ސE�����A�R�я����y�я��n�����ȊO�̏����̂����A�c����ړI�Ƃ���p���I�s�ׂ��琶���������ȊO�̈ꎞ�̏����ŘJ�����̑��̖��͎��Y�̏��n�̑Ή��Ƃ��Ă̐�����L���Ȃ����̂������B�v�ƁA�������@�ɂ���Ă���̂ł��ˁB
�@�ꎞ�����ɂ��ẮA�����ɐ���������܂����A���̂��̂��Ꭶ����Ă��܂�: �u(�P)���܂╟�����̏܋��i�A���n�⋣�ւ̕��ߋ��@(�Q)�����ی����̈ꎞ���⑹�Q�ی��̖����Ԗߋ��@(�R)�@�l���瑡�^���ꂽ���i�@(�S)�⎸���E���҂▄���������҂̎��J���v�B�����Ɣ�ׂĂǂ��ł��傤���A�u�����������ҁv�Ȃ�ċ߂��ƌ����߂������B
�@���̌����́A�X�g�b�N�I�v�V�����̏ꍇ���v���o������Ƃ��낪����܂��B�X�g�b�N�I�v�V�����̌��ł́A���傤�ǖ{���i2005�N1��25���j�A�ō��ٔ������o�ċ��^�����ɂȂ��Ă��܂��܂�������i�����V���A�������A���̃L���b�V���j�A���������̔��f���e�͕��Ă���Ƃ���ɂ��u�E�����s�̑Ή��ł���A���^�����ƌ����ׂ����v�Ƃ̂��Ƃł�����A35��Ή������l�A�Ƃ����̂��ے肵����Ȃ��Ƃ��������܂��B
�@���������甲������A���̂悤�ȃ��W�b�N�ł�: ���n���͏o���Ȃ����Ƃ̎w�E�ɑ����āA�u��t�^�҂́C������s�g���邱�Ƃɂ���āC���߂Čo�ϓI�ȗ��v���邱�Ƃ��ł�����̂Ƃ���Ă���Ƃ������Ƃ��ł���B�����ł���Ƃ���C�a�Ђ́C�㍐�l�ɑ��C�{���t�^�_��ɂ��{���X�g�b�N�I�v�V������t�^���C���̖��ɏ]���ď���̌����s�g���i�Ŋ������擾���������Ƃɂ���āC�{�������s�g�v���������̂ł���Ƃ������Ƃ��ł��邩��C�{�������s�g�v�́C�a�Ђ���㍐�l�ɗ^����ꂽ���t�ɓ�����v�B�����āA�e��Ђ��炾����ǁA��͂�u�E�����s�̑Ή��v���Ƃ��܂����B
�@�����Ŗ@28���̒�`�ł́A�u���^�����Ƃ́A��A�����A�����A�Δ�y�яܗ^���тɂ����̐�����L���鋋�^�i�ȉ����̏��ɂ����āu���^���v�Ƃ����B�j�ɌW�鏊���������B �v�Ƃ������̂ŁA��������Ė�ɓ����Ă��銴���ł��i����������o���A���Y�̏��n�Ȃǂ̑��̒�`������Ȋ����ł����ǁj�B�Ⴄ�Ǝv���̂ł����A���|���_�����o���Ȃ��Ƃ��v���܂��B�������A���ꂪ�����ɂ��w���Ȃ̂́A�o��v�オ�o���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ƃ���ł��B�ېŕW���������ɂȂ�ׂ����ǂ����́A���_���蓾��Ƃ���ł����A�펯�I�Ɍ����āA�ٌ�m��p�͍T������đR��ׂ��ł��傤�B�ł����ꂾ���ɁA�Ŗ����ǂɂƂ��Ă̓A�O���b�V�u�Ȏ咣�ł���A���v? ������܂��B�܂��A�i�ׂŐ�������邱�Ƃ���������Y�ƊE�͊��}���邩���m��Ȃ��ł��ˁi�ٌ�m�Ƃ��Ă͊��}���܂��j�B
�@���������A�������������ɂȂ��Ă̂��̈ȊO�́A���ʂ̏ꍇ�̑Ή��̎x�����ɂ��ẮA�e��Ƃ͂ǂ������Ŗ����������Ă���̂ł��傤? ����ɂ��ẮA�ނ��닋�^�����Ƃ��Č������ĐŖ��������ς܂������������I�Ȃ悤�ɂ��v���܂��B���n�����Ƃ��Ă��ꂾ���̂��߂Ɋm��\��������Ƃ����̂́A�p���ĕs�ւ����m��Ȃ��ł��B�����l����ƁA�Ή��Ƃ��Ďx�����Ζ{���͏��n���������ǁA���^�����Ƃ��Ďx�����Ă��̗l�ɐŖ��������Ă��ǂ��A�Ƃ����̂��K�Ȃ悤�Ɏv���̂ł����A����ȍٗʂ͏��Ȃ��Ƃ������̏�ł͋�����Ȃ��̂���? ����A���ۂɂ����������̂Ƃ��Ďx�������������Ă����A�Ƃ������Ƃ̂悤�ɂ��v���̂ł����i����Ƃ��Ĕ۔F�����ꍇ�ł��Ȃ���j�B
�@���ۂɉ\���̂���b�Ƃ��ẮA���Ȃ����܂ł͏��z�̗Ⴕ���Ȃ��������߂ɁA���n�����ɂ�����ׂ��Ƃ��Ă�50���~�̓��ʍT���Őŋ��͔������Ȃ������A�����������z�Ȃ̂Ŗ��ɂ��Ȃ�Ȃ������A�Ƃ������Ƃ̂悤�ɂ��v���܂��B��������ƁA���̏��u�͂��ꂩ��̖��Ȃ̂����m��܂���B
�@�c�c�ȏ�A�v�X�ɐŖ@�̏�ǂ̂ŁA���Ȃ�������ł��B�R�����g�����}���܂��B�i6��24�����M: ���������Ă�����A���ہAS����R�����g�����������A���̓ǂ݊ԈႢ���C�����邱�Ƃ��o���܂����B���肪�Ƃ��������܂��B�j
�@2004�N3��11���@�E�F�u�y�[�W�f�ځB
�@2004�N3��20���@��L���āA�����ɁA��������������₷�����邽�߂̉��M�����܂����B
�@2004�N4��3���@�R.�P�@���{�̗L���ɂ��Ă̕⑫�����M���܂����B
�@2004�N4��10���@�Q. �������w�̎咣�̋^�� �̒��ɑ����̉��M������ȂǁA�蒼�������܂����B���߂āA�E�F�u��F�X���āA���̔����ɑ���^�ۂ̘����̌������������܂����B��L�̉��M�̈ꕔ�́A���������ӌ��̈��p���ł��B���Ό����͎��グ�ĂȂ��ł����B
�@2004�N8��29���@�V. �̒��̊���̌�L���C���B
�@2005�N1��9���@�u�P�P. �a�����c�̕ɂ��āv�́u�P�P.�P�@05�N�P�����߁i�T���`15���~�j�v�����M�B10���ɂ����ɓ��o�V���̕ɂ��ĉ��M�i���ʏ����Łj�B
�@2005�N1��24���@�a���̌��ɂ��ĉ��M�B�u�P�P.�R�@�x�����Q���v��̗��R�Ɛŋ��̘b�v���B25���ɂ���ɐŋ��̘b�����M�B
�@2005�N2��27���@�a�������̕��͂Ƀ����N��t����ȂǁA��Ƀ����N���蒼�����܂����B4��4���ɂ����l�B
�@2005�N6��24���@�������n�����ɂȂ�炵�����ƂɏC���BS����̃��[���ɂ��B���肪�Ƃ��������܂��B
�@2005�N6��30���@���Q���ʌv��́A���^�����Ƃ��ꂽ�ꍇ�̑Ώ��̈Ӗ������邩���A�Ƃ����b�����M�B
�ȏ�